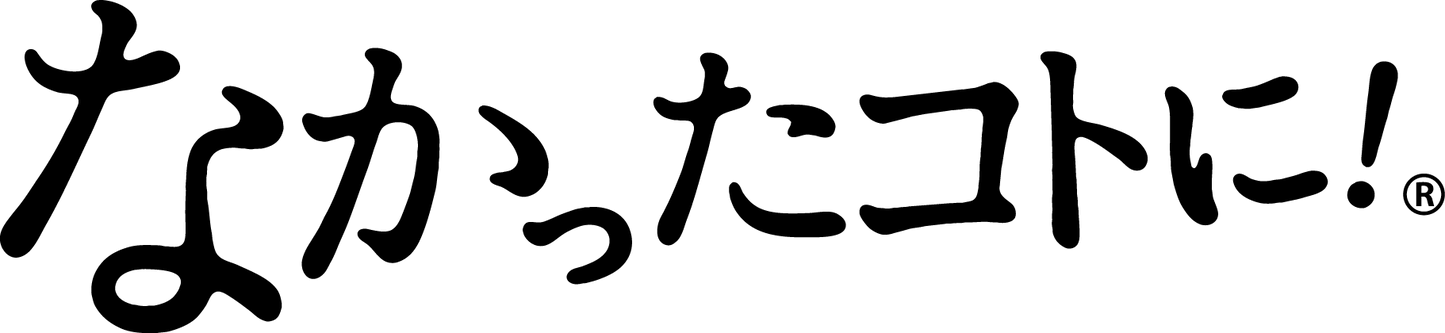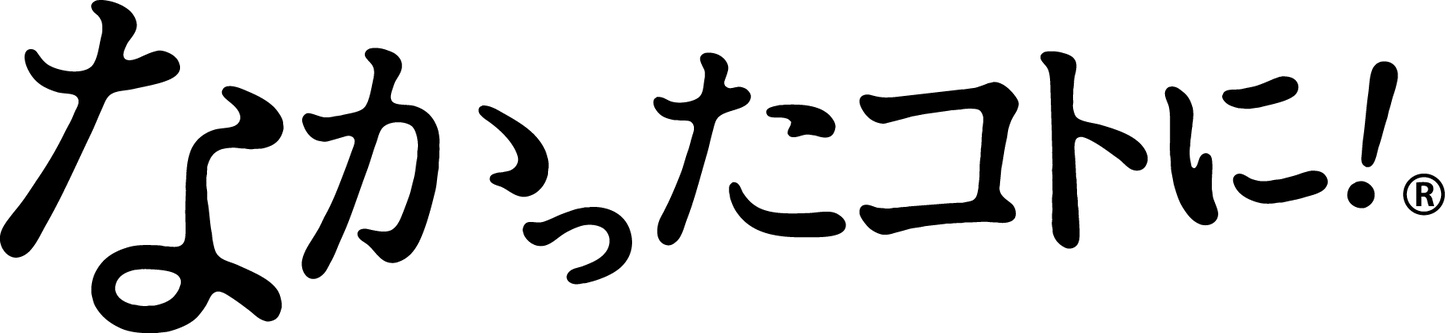- 亜鉛サプリの最適な摂取タイミングとは?正しい摂取のポイント
- 1. 亜鉛ってどんな栄養素?
- 2. 亜鉛サプリのベストな摂取タイミング
- 3. 正しい亜鉛サプリの摂取方法と注意点
- 4. 亜鉛を摂りすぎるとどんなリスクがある?
- 5. まとめ
亜鉛の不足が気になっていても、
「普段の食事でバランスよく補うことが難しい」
「亜鉛サプリの効果が活きる摂取のタイミングがイマイチわからない」
といった悩み・疑問を感じてはいませんか?
今回フォーカスを向ける亜鉛サプリは、普段の食事では十分な量を補うことが難しい亜鉛をバランスよく体内に摂りこんで、健康や美容、メンタルケアにアプローチする話題のアイテムです。
ここでは亜鉛サプリで健康や美容のインナーケアを始めようと考えている方に向けて、
・亜鉛サプリを飲む最適なタイミング
・摂取方法や注意点
・亜鉛の働き
といった基礎知識をわかりやすく解説していきたいと思います。
ぜひ最後まで参考にしてくださいね。
(2023.10.19編集)
亜鉛ってどんな栄養素?

見聞きすることが頻繁にある亜鉛という栄養素でも、健康や美容、メンタルケアにどんなアプローチができるのか、まだまだ未知な部分があるのではないでしょうか?
ここでは亜鉛がどのような栄養素なのか、特徴や効果、効果が活きる仕組みを詳しくお伝えしてみたいと思います。
亜鉛は人体に存在、身近な食べ物に含有がある栄養素
亜鉛は神経や筋肉、臓器にもともと存在している必須ミネラル群のひとつで、肉類や魚貝類、卵や乳製品といった食べ物にも多く含有されています。
身体・精神活動のサポートを司る亜鉛は、体内で産生することができず、栄養バランスの取れた食生活やサプリメントの摂取でバランスの良い補助が可能になります。
ですが現代人は、
・成人男性の場合:1日に必要な推奨量11.0㎎に比べて実際の摂取量が8.9㎎
・成人女性の場合:1日に必要な推奨量8.0㎎に比べて実際の摂取量が7.3㎎
というように亜鉛の摂取不足が問題視されるようになっています。
亜鉛は健やかな生命活動を維持するためのサポート成分でもあるため、不足すると健康や美容、メンタル面とさまざまな不調が出やすくなってしまうのです。
味覚を正常に保つ
美味しいグルメを味わって食べるために欠かすことのない味覚も、亜鉛によって正常な状態が保たれています。
亜鉛サプリを飲むタイミングが最適で、継続的に推奨量を摂取し続けていると、舌の表面に存在している味を感じ取る細胞・味蕾の数が増えて、毎回の食事を美味しく感じることができます。
丈夫な骨を育てる
加齢や運動不足、ホルモンバランスなどのゆらぎが起こると、骨は少しずつもろくなり、骨粗鬆症のリスクが高まってしまいます。
亜鉛は丈夫な骨を育てるサポートを担う栄養素で、古い骨が新しい骨に生まれ変わる新陳代謝のサイクルを正常化し、骨粗鬆症のリスクを低下させます。
骨はそもそも、筋肉や関節、皮膚を支える役割があるため、亜鉛不足になるとこれらの部位が支えられなくなり腰痛や関節痛、シワやたるみなどの深刻なトラブルにつながることがあります。
健やかなお肌づくりや育毛にアプローチする
亜鉛の美容に関するアプローチには、
・お肌や髪、筋肉の構成成分となるタンパク質を合成する
・髪を生やして成長させる役割を持つ、毛母細胞の働きを活性化する
ベストなタイミングで亜鉛サプリを正しく摂取していると、髪とお肌、筋肉を作るタンパク質の合成がスムーズになります。
するとつややかで抜け毛の少ない髪、ハリのあるお肌、バランスの取れた体型にアプローチできるようになるのです。
幸せホルモン、やる気ホルモンの産生材料になる
イライラや不安感といったストレスを頻繁に感じてしまうのは、亜鉛不足が原因のひとつかもしれません。
その理由は、亜鉛にメンタルを健やかなコンディションに整える作用があるため。
・やる気やモチベーションを高める「テストステロン」
・質の良い睡眠サイクルに働きかける「メラトニン」
・メンタル面を左右する女性ホルモン「エストロゲン」
亜鉛のメンタルケアに関する効果は、含有の多い食べ物を積極的に摂り入れたり、亜鉛サプリの摂取によって倍にアップするという興味深いエビデンスも報告されています。
亜鉛が不足するとどうなる?
亜鉛が不足する原因は、大きく分けて3つあります。
摂取不足
亜鉛を多く含む食品には魚介類、肉類、藻類、野菜類、豆類、種実類があります。
特に「魚介類や肉類」に亜鉛が多く含まれています。
その中でも、かき(養殖/生)は100gあたり14.5mgと群を抜いており、最良の亜鉛摂取源ともいわれています。
そのほかにも、うなぎの蒲焼100g(1串)には2.7mg、豚・肝臓生は100gあたり6.9mgと多く含まれています。
このような動物性タンパク質をあまり食べない人は、亜鉛不足になりやすくなります。菜食主義者のように肉を食べない人は要注意です。
吸収不全
亜鉛の1日の必要量をしっかり摂取していても、亜鉛の吸収を妨げる食材を日常的に摂取していることで結果的に亜鉛不足になることがあります。
亜鉛の吸収を妨げるものは「食品添加物」を多く含む加工食品や、植物性食品に多く含まれる「食物繊維」や「フィチン酸(穀類、豆類に多い)」といわれています。
また、コーヒー(タンニンを含む)やオレンジジュース、カルシウムも亜鉛の吸収を阻害するといわれているので注意が必要です。
排泄増加
人は利用できなかった亜鉛を、毎日身体の外へ排泄しています。
そして、病気が原因でその亜鉛排泄量が増えることがあるといわれています。
肝臓病、糖尿病、腎臓病がある人は、尿からの亜鉛排泄量が増えるといわれており、人工透析を行なっている人は亜鉛が透析の中に排出されやすいと示唆されています。
また、アルコールの摂取により亜鉛の排出量が増加するといわれています。日常的に飲酒をする人は、お酒の量も注意しましょう。
亜鉛が不足すると起こりうる症状
では、亜鉛が不足するとどうなるのでしょうか。
2018年の亜鉛欠乏症診療ガイドラインでは亜鉛不足による10の症状として以下の項目があげられています。
・皮膚炎・脱毛
・貧血
・味覚障害(舌炎)
・発育障害
・性機能不全
・食欲低下
・下痢
・骨粗しょう症
・キズの治りが遅い
・感染しやすい(易感染性)
その中でも近年、若い世代での「食生活の乱れによる亜鉛欠乏」により、味覚障害を訴える人が増えてきています。
亜鉛は、味を感じる味蕾細胞の産生に必須な成分といわれています。
亜鉛が不足することで、舌の上皮細胞に豊富になる亜鉛が減り、味を感じにくくなる味覚障害になるリスクが高まります。
舌がピリピリする、何も食べていないのに口の中が渋い、人より薄味に感じやすい、という人は要注意です。
また、亜鉛が不足することでたんぱく質やDNAの合成がうまく行えなくなり、免疫機能の低下につながります。
また、たんぱく質合成がうまく行えないことからターンオーバーがうまく行かず、皮膚炎や脱毛、爪の変形、傷が治りにくいなどさまざまな症状が起こりやすくなります。
亜鉛サプリのベストな摂取タイミング

亜鉛サプリの特徴や効果、その仕組みを学んだ今、正しい摂取タイミングがますます気になるのではないでしょうか?
ここではどのシーンで亜鉛サプリを飲むことが効果的なのか、おすすめのタイミングとそれぞれの理由をお伝えしてみたいと思います。
食後に飲むことがおすすめ
亜鉛サプリは食後に飲むことがさまざまな販売メーカーから推奨されています。
食事の後のタイミングに亜鉛サプリを飲むと、亜鉛が持つ体内吸収率の低さをカバーできたり、体外への排出スピードを遅らせることができると言われています。
目的や体調に合わせて朝・昼・夜に分けてバランスよく飲む
亜鉛サプリの1日の摂取目安量が、2~5粒程度の場合は、
・朝の摂取:一日の始まりをエネルギッシュに過ごせる
・昼の摂取:昼食時に不足しがちな亜鉛をバランスよく補える
・夜の摂取:睡眠中に減少しやすい亜鉛を補い、ホルモン分泌の活性化につながる
1日の目安摂取量が1~2粒程度の場合は、カラダやメンタル面のコンディションに合わせた朝・昼・夜の最適な摂取タイミングで、忘れずに継続摂取することがおすすめですよ。
正しい亜鉛サプリの摂取方法と注意点
亜鉛が持つ健康や美容、メンタルケアの恩恵をカラダとココロで感じ取るために、ここでは亜鉛サプリの正しい摂取方法と意外に見落としやすい注意点を詳しくお伝えしてみたいと思います。
ビタミンC含有が多い食べ物、サプリメントと併用して摂取する
亜鉛サプリの美容や健康、メンタル面に関するさまざまな効果を実感するためには、どれだけ体内への吸収を効率的にするかがポイントになります。
亜鉛サプリは特に、フルーツや野菜、緑茶などに多く含まれているビタミンCによって体内への吸収が高まることがわかっています。
亜鉛サプリを飲む際には、ビタミンC含有の多い食べ物や飲み物、サプリメントと併用して摂取しましょう。
お茶やジュースの摂取に要注意
亜鉛サプリは基本的に、水やぬるま湯で摂取することが推奨されています。
お茶やジュースで亜鉛サプリを飲んでしまうと、含有された成分が亜鉛の吸収を妨げ、効果が活きなくなる可能性があります。
亜鉛サプリを飲む際はお茶やジュースでの摂取を避け、たっぷりの水で飲むようにすると体内への吸収・保持力が高まると言われています。
3ヶ月以上継続して続けること
亜鉛サプリは体内の細胞や身近な食品に含まれる天然成分でもあるため、医薬品のように即効性を期待することが難しいと言われています。
亜鉛サプリは、
・毎日欠かさずに摂取する
・目的に応じた最適なタイミングで飲む
と同時に、3ヶ月以上続けることが推奨されています。
人間のカラダは3ヶ月程度の期間の間に、古い細胞が新しい細胞に入れ替わる新陳代謝のサイクルが備わっています。
この期間を目安に亜鉛サプリを摂取すると、新陳代謝のサイクルに合わせて栄養を補えるため、お肌や体調、精神面でのより良い変化に気づきやすくなるでしょう。
1日の目安摂取量を正しく守ること
「亜鉛サプリをたくさん飲むと効果が倍になる?」
というイメージが少なからずありますが、過剰な摂取は大きな間違いで、
・吐き気
・めまい
・腹痛
・頭痛
亜鉛ばかりではなく、美容や健康に良いどんな栄養成分でも、過度な摂取はカラダやお肌の毒になってしまうため、1日の目安摂取量を正しく守るようにしましょう。
亜鉛を摂りすぎるとどんなリスクがある?
通常、亜鉛は食事でとりすぎることは少ないといわれています。
亜鉛の過剰摂取は「サプリメントの不適切な利用」と「日常的に高濃度の亜鉛を摂取する」が原因であることが多いと示唆されています。
亜鉛をとりすぎることの弊害は「銅欠乏」のリスクが高まることです。
そのメカニズムは、亜鉛は銅と吸着しやすいタンパク質を活性化させてしまうため銅の吸収が悪くなり、銅欠乏の症状が出てくるというものです。
銅は貧血予防に欠かせないミネラルで、亜鉛をとりすぎることで、以下のような症状が出てくる可能性があります。
<銅欠乏の症状>貧血、疲労感
銅は赤血球のヘモグロビンがつくられる時に必要な酵素の成分です。
ヘモグロビンの材料である鉄が充分でも、銅が不足していると貧血になるリスクが高まります。
<銅欠乏の症状>骨異常、毛髪異常
銅は、骨や結合阻止くの形成をサポートする酵素の構成要素であるため、不足すると骨や毛髪の異常が生じる場合もあります。
<銅欠乏の症状>手足にチクチクする感覚がある
銅が不足すると、心血管系や神経系の異常が生じて手足にチクチクする感覚や感覚消失が起こることがあります。
<銅欠乏の症状>成長障害
銅が不足することで発育遅延などの成長障害が起こりやすくなる可能性があります。
また、亜鉛をサプリメントで過剰に摂取した場合は、以下のような副作用が生じる場合があります。
・頭痛
・発熱や倦怠感、神経障害
・下痢、吐き気、食欲不振
・HDLコレステロール(善玉コレステロール)の低下
特に、1日あたり100mgを超える亜鉛摂取をする男性は「進行性前立腺がんのリスク」が2.29倍に上昇するという報告もあります。
亜鉛サプリを利用する際は、過剰摂取にならないように商品に記載されている1日の摂取目安量をまもりましょう。
まとめ
亜鉛サプリは食生活が乱れがちで亜鉛不足が気になるすべての方に、効率的に栄養を補えるおすすめのアイテムです。
亜鉛サプリの販売メーカーによっては、吸収を高める成分やサポートの栄養素が含まれている製品も!
ベストな亜鉛サプリを選んで継続的な摂取を心がけながら、カラダの内側からの健康・美容・メンタルケアにアプローチしていきましょう。
※本記事は管理栄養士監修のもと作成しております
← 一覧に戻る